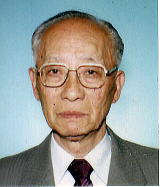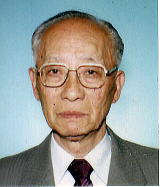
|
新年度を迎え、小金井支部も定時総会は18回となります。18年も経つと活動家も活動内容も結構変わります。当然でしょう。ところが、そうでない例が出て来ました。 それは、去る5月16日に実施された協議員会・学員総会のときのことでした。大田支部藤井政男副会長が「学員会会長の選任は、我が国の大学を取り巻く激動の時代であり、従来によるものではなく、全学員の代表である協議員に対して、開かれた方法を取るべきだと思う。従って、学員会会長の選任につては、一定の推薦者のあることを前提として、期間を限定して告示する立候補制をとった方が良いと思う。そして、学員会会長候補者は、来年の協議員会で演説などを聞いて採択すべきだと思う。」さらに、この発言に続いて、會澤伸憲幹事長は、「従来の方法で会長を選出するのであれば、協議員の意見が反映されない恐れがあると思う。会長選出の方法を見直す考えはないか。」と質問しました。山本隆幸議長(弁護士)は、提案に対して反対意見を十分討議することもなく、拍手多数ということで提案は否決されたと宣言しました。 学員会本部は、規約より内規や慣行を大事にする傾向があり、私の経験によると誰が選考委員に選ばれるか、次に学員会会長候補を複数だすか、学員会幹事会の結果を注目したいと思います。 正野建樹学員会副会長は、第2回白門ミーテイングで「凋落しかけている母校が進展するために頑張っていきたい。」と述べたようですが、真っ先に改革すべきは、学員会本部ではないでしょうか。 新会長誕生は1年後に迫っています。学員会皆様のお考えはいかかでしょうか。 |
平成27年度